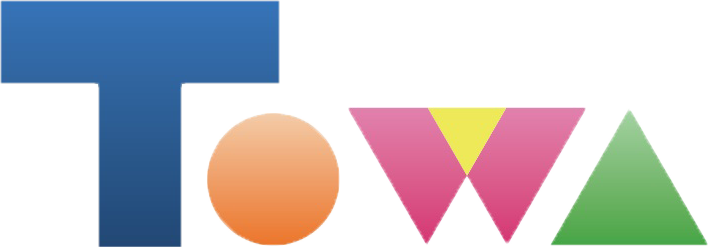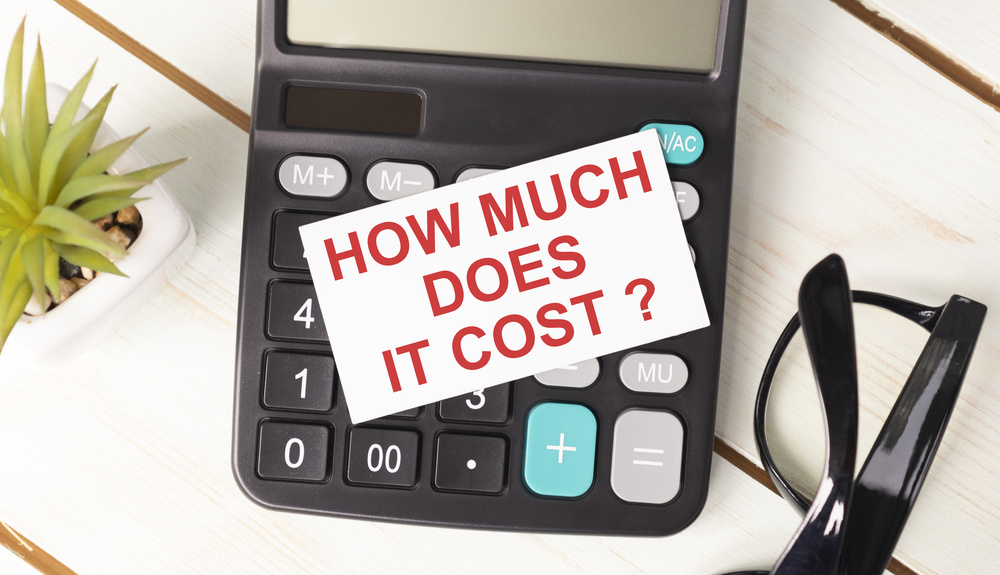建物で過ごす人々の健康を維持するための空気環境測定基準のまとめ|お役立ちコラム
COLUMN
コラム
2025.03.16
- 環境衛生管理
- 空気環境測定
建物で過ごす人々の健康を維持するための空気環境測定基準のまとめ

空気環境測定と言われても・・・。
ビル管理法の空気環境測定を行わなければならないが、そもそもこの測定は何を測るのか?わからないことだらけでお悩みになっている方も多いのではないでしょうか。
空気環境測定は建築物における衛生的環境の確保に関する法律で定められた測定を行い建物で過ごす人々に衛生的な環境を提供していただくためにも測定の内容を是非知ってほしいものです。
ここでは空気環境測定の測定基準について分かりやすく解説を行いました。
建物の管理のためにも是非記事を参考にしてください。

1.空気環境測定基準とは
空気環境測定には7項目の数値の測定基準があります。建物に空気調和設備を設けている場合は環境衛生上、良好な状態を維持するための基準として厚生労働大臣が定めた基準です。
しかしながら基準値を越えたからといって直ちに体調不良につながるわけではありませんが建物で働いたり過ごす人々に不快感を与え仕事の生産性にも影響を与える可能性があるために常に良好な状態にする必要があります。
空気環境測定では①温度、②湿度、③気流、④一酸化炭素、⑤二酸化炭素、⑥粉塵の6つの項目で測定を行います。また、それぞれの項目には測定基準があります。基準を超えると体に不快感を感じるようになります。
それでは順番に見てまいりましょう。

1-1.温 度
基準値は17℃以上~28℃以下で、外気との差が5~7℃が快適な条件となっています
基準値を大きく超えるとのぼせ、低いと寒いため仕事の作業効率が落ちていきます。特に、過度な冷房では胃腸障害や体の痛みを訴える人、疲れやすくなったり風邪をひきやすくなったりするなどいわゆる冷房病が懸念されるため十分な配慮が必要です。
対策としては空調機の温度調整で適正温度に設定するようにします
1-2.湿 度
基準値は40%以上~70%以下で基準値を大きく超えると不快指数が上がり作業効率が落ちてきます。低いと菌に感染しやすくなり風邪をひきやすくなります。
湿度は冷房時に高湿になりやすくまた暖房時には低湿になりやすくなります。
暖房の時期に湿度が低い状態で長期間生活すると鼻やのどの粘膜が乾燥し、不快感やひどくなると感染症を起こしやすくなります。
対策としては、湿度が高い場合は除湿器、低い場合は加湿器の設置をお勧めします。
1-3.二酸化炭素
基準値は1,000PPM以下です。基準値を大きく超えると頭痛・耳鳴り・めまいなどの体調不良につながり、また眠気を誘います。
人の呼気には約4%の二酸化炭素が含まれており二酸化炭素それ自体はよほど高濃度でない限り人体には有害を及ぼしません。この二酸化炭素は室内の汚染状況を示す指標としての役割を持っています。
労働衛生関係法令では一般事務所は0.5%以下でなければならないと規定しています。ビル管理法では働く人の衛生上良好な状態の実現を目指して0.1%以下(1,000ppm)とさらに高いレベルを目指しています。
対策としては換気をしたり窓をあけ空気の取り入れや入替えを行います。
1-4.一酸化炭素
基準値は10PPM以下です。基準値を大きく超えると頭痛・はきけ・めまいなどの体調不良に繋がります。
一酸化炭素は人体に有害を及ぼします。特に一酸化中毒を起こすとひどい場合は中毒死が起き、死に至らなくとも脳梗塞等の後遺症が起きるなど人体に対する影響は重大です。
空気環境測定基準では人体への影響を考慮してその含有率を10PPM以下と定めていますがそもそも大気中の一酸化炭素の含有率が20PPM以上あるため基準以下を維持できない建築物の場合は特例として20ppmまで認めることとしています。
対策としては換気をしたり窓をあけ空気の取り入れや入替えを行います。
1-5.気 流
基準値は0.5m/s以下です。基準値を大きく超えると不快感が出て集中力が落ちてきます。
気流については空調の吹出速度が大きな影響を与えます。吹出速度が速すぎると人は気流の影響を直接受けドラフトと呼ばれる不快感を感じる事になります。逆に速度が遅すぎると室内で十分に空気が拡散せずに室内の熱が不均衡になり、また浮遊粉塵や有毒ガスが室内に滞留することになるので適切な吹出速度にすることが重要です。
対策としては空調からの吹出しの風が直接当たらないようにしてください。
1-6.浮遊粉塵
基準値は0.15mg/m³以下です。基準値を大きく超えると微粒粒子を鼻から吸い込み肺にたまり体調不良につながります。
粉塵は室内に堆積、付着しているものが歩いたりしたときの風によって飛散したりしたものと、自動車排出ガス中に含有されるものや土砂の巻上等によって大気中の浮遊粉塵が室内に流入してきたものと大きく2つに大別されます。
浮遊粉塵で10µm以上の大きさは鼻やのどでほとんどが補足されますが 、10 µm 以下の粉塵となると起動や肺胞に達するといわれていることからビル管理法の基準では粒径10 µm 以下を対象とすることになっています。
対策としては、空調器に高性能フィルターを設置したり空気清浄器の設置をお勧めします。
2.まとめ
空気環境測定では温度、湿度、気流、一酸化炭素、二酸化炭素、粉塵の6つの項目で測定を行います。厚生労働省が定めた基準を超えると体に不快感を感じるようになるので対策をとる必要があります。
温度が基準値を超えた場合は空調機で温度調整を行ってください。
湿度が基準値を超えた場合は、除湿器や加湿器を設置して調整を行ってください。
一酸化炭素や二酸化炭素が基準値を超えた場合は、窓を開けたりして換気を行い空気の入替えをしてください。
気流が基準値を超えた場合は、空調からの吹出しの風が直接当たらないようにしてください。
浮遊粉塵が基準値を超えた場合は、空調器に高性能フィルターを設置したり空気清浄器の設置をお勧めします。
空気環境測定の結果を元に、人々の健康を守るためにも職場環境の改善に取り組んでいただきたいと思います。
ビル管理法の空気環境測定についてもっと知りたい方は当ブログ「ビル管理法の空気環境測定で衛生的環境を実現する為のポイント解説」でわかりやすく解説しています。

おすすめの関連記事
ピックアップ
CATEGORY
POPULAR